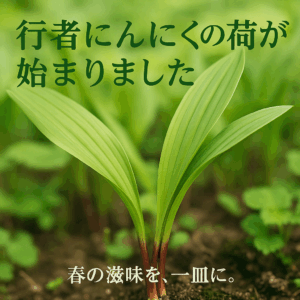今日の松ぼっくり
津軽いろ葉のまわりには、自然の恵みがあふれています。春の山菜、夏の緑陰、秋の実り、そして冬の静けさ。そのすべてが、私たちの暮らしや仕事に寄り添ってくれています。今日は、そんななかでもふと足元に転がっていた、可愛らしい自然の贈りもの――松ぼっくりのお話です。
お散歩の途中、地面にいくつも落ちている松ぼっくりを見つけました。ころんとしたその形と、ひとつひとつのウロコのような構造がなんとも愛らしい。思わずしゃがみこんで撮った一枚が、今日のブログの写真です。

津軽のこの辺りでは、特に秋から冬にかけて、いたるところに松ぼっくりが落ちています。子どものころは集めて遊んだり、工作に使ったりしたものですが、大人になってからその仕組みを知ると、また違った驚きがあるものです。
実は、松ぼっくりのウロコのような部分――“鱗片(りんぺん)”と呼ばれる部分――は、湿度によって開いたり閉じたりする性質を持っています。乾燥している日は開いていて、雨が降ったり湿気が高い日には閉じている。まるで生き物のように、環境に反応して姿を変えるその様子は、見ているだけで楽しくなります。
この不思議な動き、実は「細胞の構造」が関係しています。松ぼっくりの鱗片は、2種類の異なる細胞層からできています。外側の細胞層と内側の細胞層で、それぞれが水分を含んだときと乾燥したときの“縮み方”が違うのです。具体的には、内側の層は乾燥に強くあまり収縮しませんが、外側の層は水分を失うと大きく縮みます。
この「収縮率の差」が曲がる力となって、鱗片全体を反らせたり閉じたりしているのです。まるでバイメタルのように、二つの性質の違う素材が組み合わさることで、自然に動きを生み出している――これが松ぼっくりの湿度応答メカニズムです。
この仕組みは「パッシブアクチュエーター」とも呼ばれ、人工の材料や建築にも応用されはじめています。エネルギーを使わず、自然の力だけで動く。私たちが目にする自然の造形の中には、こんなにも優れた仕組みが隠れているのだと、あらためて感動してしまいます。
身近な松ぼっくりに、こんな仕掛けがあるなんて、なんだか面白いですよね。
これからも、津軽いろ葉のまわりで見つけた小さな自然の不思議を、少しずつご紹介していけたらと思います。次はどんな発見があるでしょうか。お楽しみに。
投稿者プロフィール

- 青森県五所川原市相内で生まれ育ちました。大学進学を機に東京に出て、今は相内と東京を行き来しながら、仕事と子育てに追われる毎日を送っています。相内の自然や人のあたたかさ、東京の華やかで刺激的な世界、そのどちらも大好きです。そんな私だからこそできる「津軽の恵み」の届け方があると思い、このプロジェクトを立ち上げました。どうぞよろしくお願いします。
最新の投稿
 お知らせ2025年9月30日青森の誇り「田酒 百四拾」に心奪われました
お知らせ2025年9月30日青森の誇り「田酒 百四拾」に心奪われました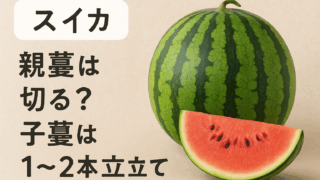 お知らせ2025年8月24日スイカの親蔓と子蔓の秘密 ― カボチャとの違いにびっくり!
お知らせ2025年8月24日スイカの親蔓と子蔓の秘密 ― カボチャとの違いにびっくり! お知らせ2025年8月17日富麗華25周年と溢れる花々を見て
お知らせ2025年8月17日富麗華25周年と溢れる花々を見て お知らせ2025年7月22日【募集】宝石を育む喜びを分かち合う「津軽ブルーベリーオーナー制度」
お知らせ2025年7月22日【募集】宝石を育む喜びを分かち合う「津軽ブルーベリーオーナー制度」