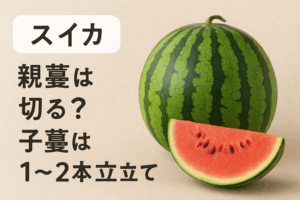青森の誇り「田酒 百四拾」に心奪われました
少しずつ秋の気配が深まってきましたね。美味しいものがたくさん出回るこの季節、ついつい食いしん坊の血が騒いでしまいます。
実は昨日お邪魔したお店で、しばらく忘れられないかもしれない、とっても素敵な出会いをしてしまったんです。それは、ずっとずっと憧れていた、青森が誇る一本の日本酒との出会いでした。
その名も、「田酒 百四拾(でんしゅ ひゃくよんじゅう)」。
日本酒がお好きな方なら、この名前を聞いただけで「えっ!」と驚かれるかもしれません。そう、あの「田酒」の、それも特別なお酒です。今日は、その奇跡のような出会いと、心までとろけてしまった感動の味わいについて、少しだけ熱く語らせてください!
本題に入る前に、まずは「田酒」そのものについて少しだけお話しさせてくださいね。
「田酒」は、青森県にある西田酒造店さんが造っている日本酒です。「田」んぼの「酒」と書いて「でんしゅ」と読みます。その名前には、「お酒の原料であるお米は、すべて田んぼから生まれるもの。その原点に立ち返り、田んぼの米だけで美味しいお酒を造りたい」という、蔵元さんの熱い想いが込められているんです。
その言葉通り、「田酒」は醸造アルコール(お米以外の原料から作られたアルコール)を一切添加しない「純米酒」しか造っていません。まさに、お米の旨味を真っ直ぐに味わえる、日本酒の王道とも言えるお酒なのです。
その味わいは、すっきりとしていながらもお米のふくよかな旨味がしっかりと感じられて、本当に美味しいんです。だから、地元青森ではもちろんのこと、今や全国に熱烈なファンがいる、まさに青森を代表するスター選手のような存在!
でも、その人気がすごすぎて、ちょっとした問題(?)も起きているんです。
というのも、西田酒造店さんは、あまりの人気に生産が追い付かなくなり、丁寧な酒造りと安定した供給を両立させるために、数年前に思い切った決断をされました。それは、お酒を卸す「特約店」と呼ばれる酒屋さんを、ぐっと絞り込むことだったんです。
その結果、長年「田酒」を取り扱ってきた都内の酒屋さんですら、取引が打ち切りになってしまうという事態が起きました。今では、限られたお店でしか手に入れることができず、もし見かけたとしても、一人一本までだったり…。いつしか「幻のお酒」なんて呼ばれるようにもなりました。
そんな背景を知っているからこそ、飲食店でお酒をお任せでお願いして、お料理にあわせて出していただけると、「おっ!」と嬉しくなってしまうんですよね。
しかも、
田酒 百四拾
…え?
ひゃ、ひゃくよんじゅう…?
思わず二度見、三度見してしまいました。ただでさえ貴重な「田酒」の中でも、この「百四拾」は、さらに特別な限定品。まさかこんな場所で出会えるなんて! 心臓がドキドキと高鳴るのを感じながら頂きました。
お酒はそれほど強くない私ですが、この機会を逃したら一生後悔する! そんな確信があったんです。
天国の味わい。フルーティーな香りと絹のような舌触り
やがて、杜氏さんの想いがこもった貴重な一滴が、美しいグラスに注がれました。
そっと鼻を近づけると、ふわっと立ち上る、信じられないくらい華やかで甘い香り…! まるで完熟したメロンや洋梨のような、瑞々しいフルーツを思わせる吟醸香に、飲む前からうっとりしてしまいます。日本酒って、こんなにフルーティーな香りがするんだ…!
期待に胸を膨らませて、一口。
美味しい!
舌に触れた瞬間、まず感じたのは、絹のようになめらかな口当たり。そして次の瞬間、口いっぱいに広がるのは、香りそのままの上品で優しい甘みと、お米の旨味が凝縮された豊かなコク。
でも、甘ったるいわけでは決してなくて、後味は驚くほどすっきりと綺麗に消えていくんです。このキレの良さがあるから、次の一口、また次の一口と、ついつい杯が進んでしまいます。
「これ、本当に日本酒…?」
普段、日本酒を飲むとすぐに顔が赤くなってしまう私ですが、この「田酒 百四拾」は、あまりの美味しさにそんなことも忘れてしまうほど。アルコールの角が全く感じられなくて、すーっと身体に染み込んでいくような優しい味わいでした。これは、お酒が苦手な女性にこそ飲んでみてほしい一杯かもしれません。あまりの美味しさに、ちょっと危険ですけどね(笑)。
うんちくタイム!「百四拾」に込められた、復活の物語
あまりの美味しさに感動して、「この『百四拾』っていう名前には、何か意味があるんですか?」とお店の方に尋ねてみると、 fascinatingな物語を教えてくれました。
このお酒に使われているお米は、「古城錦(こじょうにしき)」という名前の酒米。実はこのお米、もともとは明治時代に青森県で開発されたものの、時代の流れの中で一度栽培が途絶え、「幻の米」となっていたんだそうです。
その古城錦を復活させよう!と、一大プロジェクトが始動しました。ところが、 やっとのことで復活させた種籾を詳しく調べてみると、なんと別のお米の品種(「豊盃」という別のお酒の親である「陸羽132号」)が混ざってしまっていることが判明したんです!
普通なら諦めてしまいそうな状況ですよね。でも、蔵人さんたちは諦めませんでした。そこから気の遠くなるような年月をかけて、手作業で一粒一粒、純粋な「古城錦」だけを選別し直し、見事、本来の「古城錦」を蘇らせることに成功したのです。
そして、このお酒「百四拾」という名前は、その復活を遂げた「古城錦」が、もともと持っていた品種番号「青系酒140号」にちなんで名付けられたんだとか。
つまり、この一杯には、幻の米を追い求めた蔵人さんたちの、とてつもない情熱とロマン、そして青森の酒造りの歴史そのものが、ぎゅっと詰まっているんですね。
そんな物語を知ってから飲む「百四拾」は、また格別の味わいでした。ただ「美味しい」だけじゃない。一杯の向こう側にあるたくさんの人々の顔や、青森の豊かな田園風景が目に浮かぶようでした。ああ、なんてありがたい一杯なんだろう…と、自然と感謝の気持ちが湧き上がってきました。
さて、こんなに美味しいお酒を一人で楽しむのはもったいない! もちろん、最高のお供も一緒です。

私が「百四拾」と一緒にいただいたのは、「カマスの炭火焼き」。
脂ののった身が、田酒のフルーティーな酸味と絶妙にマッチして、オイシイ。 冷酒の爽やかさが、カマスのほのかな甘みを引き立ててくれました。
その後、締めくくりは青森産の十割そばにイクラをのせた一品。十割そばって、そば粉100%で作るから、風味が濃厚なんですよね。青森のそばは、冷涼な気候で育つそばの実が上質で、ツルツルとした食感が魅力。そこに、青森産の新鮮なイクラをトッピングして、青森ずくしのメニューに仕上げました。イクラのプチプチとした食感と、そばの素朴な味わいが合わさって、口いっぱいに広がる幸せ! 田酒の余韻が残る中で食べると、フルーティーな風味がイクラの塩味をマイルドにしてくれました。

振り返ってみると、田酒「百四拾」はただのお酒じゃなくて、青森の文化や歴史を凝縮した一本だって実感しました。全国的に人気があるのも納得で、希少性が高い分、出会えた喜びが大きいんです。冷酒で飲むフルーティーさは、女性やお酒初心者さんに特におすすめ。
もちろん、飲み過ぎは注意ですよ(私も1杯で満足でした)。
青森の魅力をもっと知りたくなったら、津軽いろ葉のブログをチェックしてくださいね。次回は、青森の他の地酒について書くかも?
皆さんのコメント、お待ちしてます♪
投稿者プロフィール

- 青森県五所川原市相内で生まれ育ちました。大学進学を機に東京に出て、今は相内と東京を行き来しながら、仕事と子育てに追われる毎日を送っています。相内の自然や人のあたたかさ、東京の華やかで刺激的な世界、そのどちらも大好きです。そんな私だからこそできる「津軽の恵み」の届け方があると思い、このプロジェクトを立ち上げました。どうぞよろしくお願いします。
最新の投稿
 お知らせ2025年9月30日青森の誇り「田酒 百四拾」に心奪われました
お知らせ2025年9月30日青森の誇り「田酒 百四拾」に心奪われました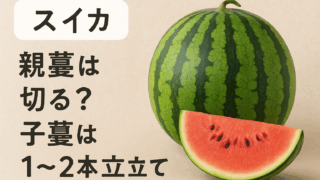 お知らせ2025年8月24日スイカの親蔓と子蔓の秘密 ― カボチャとの違いにびっくり!
お知らせ2025年8月24日スイカの親蔓と子蔓の秘密 ― カボチャとの違いにびっくり! お知らせ2025年8月17日富麗華25周年と溢れる花々を見て
お知らせ2025年8月17日富麗華25周年と溢れる花々を見て お知らせ2025年7月22日【募集】宝石を育む喜びを分かち合う「津軽ブルーベリーオーナー制度」
お知らせ2025年7月22日【募集】宝石を育む喜びを分かち合う「津軽ブルーベリーオーナー制度」