幻の魚・ヤツメウナギを探して ~川辺に響く遠い記憶~
津軽いろ葉の近くを流れる川にも、かつては「ヤツメウナギ(八目鰻)」が姿を見せていたと、よく聞いたものです。細長く、吸盤のような口を持つその姿は、子どもながらにとても不思議で、「なんだか古代からの生き物みたい」と印象的でした。近年では「幻の魚」と呼ばれるほど、その姿を目にする機会は激減しています。

昔の “川の恵み”、ヤツメウナギ
地域では、ヤツメウナギを食用にしてきた歴史があります。津軽では、ぶつ切りにしたヤツメウナギを味噌汁にするのが一般的な食べ方でした。肝や内蔵のコクが溶け出した味噌汁は、滋味深く、地方ならではの味。
昨年、地元の方が「今日はヤツメウナギ大漁だった」と話しているのを聞き、一瞬「まだたくさん生息しているんだ」とほっとしました。実際に採った人は売るほど採れたそうです。
ただ、その翌日には話題にもならず、「やっぱり少しの奇跡だったのか…」と複雑な思いになりました。
激減の影にある6つの理由
インターネットで調べてみると、ヤツメウナギが全国的に減少している背景には、いくつかの要因が重なっているようです。
1. ダムなどによる遡上阻害
ヤツメウナギはサケやウナギと同じく遡上性があり、産卵のために川を遡る必要があります。しかし、水力発電所や灌漑用のダムが建設されるにつれ、産卵ができる場所へのアクセスが阻まれていると、国内外の研究で指摘されています。
2. 川岸の環境破壊
川岸に植生が失われることで、水温が上がりすぎてヤツメウナギの幼生や産卵環境に悪影響が及ぶという報告もあります。
3. 水質汚染・農薬の流入
農業の発展に伴い、農薬や肥料が河川に流入。これがヤツメウナギの生育や産卵に必要な微生物環境に害を及ぼしていると考えられています。
4. 捕獲圧・漁具の変化
天然物しかないにもかかわらず、乱獲や漁具の効率向上によって採れる数が減少。地域によっては「1トン以下になった」との記録もあります。
5. 養殖の困難さ
ウナギとは異なり、ヤツメウナギは人工養殖が非常に難しく、市場に出回るのはほぼ天然だけに依存しています。
6. 捕食者の影響・外来種の脅威
海外ではヤツメウナギ類が外来種として生態系に影響を与える例もありますが、日本では主に捕食や生息環境の変化による影響が懸念されています。
自然との調和を考えるきっかけに
昨年の大漁の噂は、やはりヤツメウナギがまだ私たちの川に生きている証拠でしょう。でも、それが続かないのは、上述したような環境の変化が原因だという見方が現実です。
それでも希望があります。フィンランドやアメリカでは、放流活動や産卵環境の整備によって一部でヤツメウナギ類の回復が見られているという報告があります。日本でも、幼生の調査や放流研究に取り組む動きが広がりつつあります。
私たちにできること
- 川岸に植生を取り戻す活動
松などの木を植えて、川の日陰や水温低下を保つ取り組み。 - ダムや水門への配慮
ヤツメウナギが遡上できるような工夫や魚道の設置検討。 - 調査・放流支援
地元や自治体の生態調査や放流事業に、ボランティアとして参加。 - 生活の見直し
農薬や洗剤など日常生活で河川に流れる物質を減らす努力。
幻の魚とともに、次世代へつなぐ未来を
子どもの頃に味わったヤツメウナギの味噌汁、そして昨年の小さな大漁。この2つの体験があるからこそ、私はこの地域の環境や未来に向けて、今何か行動したいという気持ちが強くなりました。
「幻の魚」と言われるその一方で、まだ“川底に息づく命”としてヤツメウナギは存在しています。その声を聞き、声を届けることが、未来の子どもたちにもこの味を残す一歩だと思います。
投稿者プロフィール

- 青森県五所川原市相内で生まれ育ちました。大学進学を機に東京に出て、今は相内と東京を行き来しながら、仕事と子育てに追われる毎日を送っています。相内の自然や人のあたたかさ、東京の華やかで刺激的な世界、そのどちらも大好きです。そんな私だからこそできる「津軽の恵み」の届け方があると思い、このプロジェクトを立ち上げました。どうぞよろしくお願いします。
最新の投稿
 お知らせ2025年9月30日青森の誇り「田酒 百四拾」に心奪われました
お知らせ2025年9月30日青森の誇り「田酒 百四拾」に心奪われました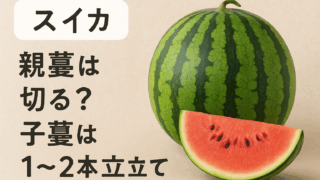 お知らせ2025年8月24日スイカの親蔓と子蔓の秘密 ― カボチャとの違いにびっくり!
お知らせ2025年8月24日スイカの親蔓と子蔓の秘密 ― カボチャとの違いにびっくり! お知らせ2025年8月17日富麗華25周年と溢れる花々を見て
お知らせ2025年8月17日富麗華25周年と溢れる花々を見て お知らせ2025年7月22日【募集】宝石を育む喜びを分かち合う「津軽ブルーベリーオーナー制度」
お知らせ2025年7月22日【募集】宝石を育む喜びを分かち合う「津軽ブルーベリーオーナー制度」


