相内の虫送り──藁龍の先に見えた、文化の灯と20年ぶりの再会
2025年6月14日。青空に恵まれた土曜日、五所川原市相内で、今年も「虫送り」が行われました。田植えを終えたこの時期、五穀豊穣と無病息災を願って村内を練り歩くこの行事は、津軽地方に古くから伝わる大切な民俗行事であり、現在では無形文化財として受け継がれています。
虫送りの起源は、農業にとって三大災厄とされた「風」「日照り」「害虫」のうち、唯一人の手で“祓える”と信じられていた害虫を煙や祈りで追い払おうとしたことに始まると言われています。その祈りは、やがて信仰と結びつき、村の大切な年中行事へと姿を変えていきました。
津軽一円で行われていた虫送りも、今ではごく一部の地域にしか残っていません。中でも相内の虫送りは、「津軽地方の虫送りの原型」とされ、伝統と格式を色濃く残しています。
私も、実はこの虫送りに小学生の頃参加したことがありました。あの頃の記憶は、夏が近づく湿った風と、太鼓や笛の音に包まれて、夕暮れの中を夢中で歩いた思い出として、今でも心の奥に残っています。
久しぶりに見た虫送りは、記憶よりもずっと迫力のあるものでした。行列の先頭を飾るのは、藁で精巧につくられた長い龍のような「ムシ」。実際にはこれが「虫」そのものであり、村中を練り歩いたのち、相内神明宮の松にくくりつけられ、村を1年間守るのです。
(※動画の画素数を落としてあるのは、個人が特定されない程度に不鮮明にすることを目的とした加工です)
龍の後には、太刀を片手に勇ましく舞う「太刀振り」のハネトたちが続きます。この太刀振りは、坂上田村麻呂が蝦夷征伐の際に太刀を振って敵を追い払ったという伝説に由来しているとされ、ここ相内では、太刀の形が稲穂に似せられているのが特徴です。
笛や太鼓の囃子、コミカルに跳ねる荒馬、小さな虫を担ぐ人、酒樽をかつぐ道化役…それぞれがしっかりと役割を持ち、この行事を彩ります。しかも今では小学生だけでなく、中学生も多く参加していて、少子化の影響もあるのか、地域ぐるみで未来に伝えていこうという意志が感じられました。
(※動画の画素数を落としてあるのは、個人が特定されない程度に不鮮明にすることを目的とした加工です)
そして、今年の虫送りでもう一つ、私にとって忘れられない出来事がありました。
行列を見物していた最中、ふと目が合った人が! なんと、20年ぶりに再会する小中学校の同級生だったのです。名前を聞く前に、お互い誰だかわかってしまったのだから、これはすごいご利益。虫送りが神事であることを、心から実感する瞬間でした。
昔から続く祭りは、ただの伝統行事ではありません。地域の人々の祈り、つながり、そして時間を越えて結ばれる縁を生み出す力を秘めています。
これからも相内の虫送りが、地域の宝として、そして人々の心をつなぐ灯火として、末永く続いていくことを願ってやみません。
投稿者プロフィール

- 青森県五所川原市相内で生まれ育ちました。大学進学を機に東京に出て、今は相内と東京を行き来しながら、仕事と子育てに追われる毎日を送っています。相内の自然や人のあたたかさ、東京の華やかで刺激的な世界、そのどちらも大好きです。そんな私だからこそできる「津軽の恵み」の届け方があると思い、このプロジェクトを立ち上げました。どうぞよろしくお願いします。
最新の投稿
 お知らせ2025年9月30日青森の誇り「田酒 百四拾」に心奪われました
お知らせ2025年9月30日青森の誇り「田酒 百四拾」に心奪われました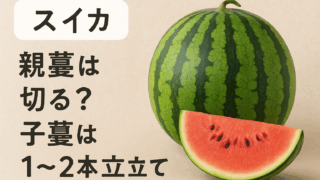 お知らせ2025年8月24日スイカの親蔓と子蔓の秘密 ― カボチャとの違いにびっくり!
お知らせ2025年8月24日スイカの親蔓と子蔓の秘密 ― カボチャとの違いにびっくり! お知らせ2025年8月17日富麗華25周年と溢れる花々を見て
お知らせ2025年8月17日富麗華25周年と溢れる花々を見て お知らせ2025年7月22日【募集】宝石を育む喜びを分かち合う「津軽ブルーベリーオーナー制度」
お知らせ2025年7月22日【募集】宝石を育む喜びを分かち合う「津軽ブルーベリーオーナー制度」


